アフォーダンスと保育の環境 ― 2014/05/26
アフォーダンスの研究者、細田直哉先生(聖隷クリストファー大学)と、保育環境について対談しました。
「保育における環境構成とアフォーダンス」『げんき』No143、エイデル研究所、2014
143号のテーマは、「子どもの育ちと保育環境」
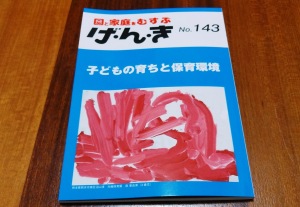
対談は、研究会の前に教室で行いました。対談を読んだ家族からは、細田先生の真摯で誠実な姿勢に対して、私の座り方が「偉そう」と批判が。え~そうなの~? 私は、自分の写真を見たときに(肩が上がって胸をすぼめて、えらく緊張した姿勢をしているな。いくつになったら人と話をするのに緊張しなくなるんだろうか)と、思っていたのに。「知らない人が写真を見たら偉そうな人に見える」と言われてびっくり。

でもまあ写真は抜きにして、中身はとても濃い内容です。
「子どもは『心』だけで生きているのではありません。『心身』まるごとで『環境』にかかわり、『環境』を自分の一部としながら発達しています』といった珠玉のような細田先生の言葉が並びます。
18ページに渡る対談の内容は、環境構成に長く取り組んでこられた先生方にもきっと満足いただけるのではないかと思います。普段、研究会でおしゃべりしている内容を、アフォーダンスの理論と保育の実践とをつなぐ対談として、公にできてとてもうれしいです。
またこの号では、色彩の専門家である宮内博実先生(静岡文化芸術大学名誉教授)も登場。
「子どもの育つ環境と色の世界」と題して、保育環境の色彩について語られています。

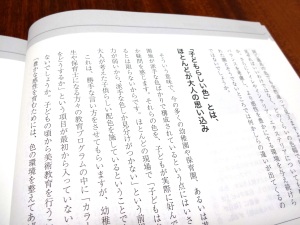
色の違いを見分ける弁別力は、4歳でほぼ大人と同じに。
幼児期に豊かなカラーボキャブラリーを。
子どもらしい色は、ほとんどが大人の思い込み。
民族性・エリアによって、好まれる色は変わる。
幼稚園・保育園の色彩環境は家庭の延長であるべき、といった内容が並びます。
保育環境や教材を、色彩の観点から見直すヒントが満載です。
