「飾らない保育環境」を連載中 ― 2013/08/01
小学館「新幼児と保育」で、今年は、「飾らない保育環境」を連載しています。
とはいっても、私の書き下ろしではなく、実際に記事を書いているのは小学館のエディター、神崎典子さん。
神崎さんが私にインタビューをして書き、それを私が校正します。「○○先生監修」と書かれている記事や本は、その先生が直接書いていないことを示しています。聡明な編集者の方がまとめてくださった内容は、私が書く文章よりも読みやすいことが多いものです。
とはいっても、私の書き下ろしではなく、実際に記事を書いているのは小学館のエディター、神崎典子さん。
神崎さんが私にインタビューをして書き、それを私が校正します。「○○先生監修」と書かれている記事や本は、その先生が直接書いていないことを示しています。聡明な編集者の方がまとめてくださった内容は、私が書く文章よりも読みやすいことが多いものです。

4・5月号から並んだ「新幼児と保育」。今月、池袋のジュンク堂書店では、平積みになっていました。
「飾らない保育環境」は、4・5月号の環境構成とは何か、環境の要素の説明から始まりました。
「飾らない保育環境」は、4・5月号の環境構成とは何か、環境の要素の説明から始まりました。

6・7月号は「感性を育てる色彩の調和」。8歳頃までの環境で育つと言われる色彩感覚。保育室内の色彩環境に、こだわりました。色彩分析で、色の調和が良いと評価された園の写真を使っています。
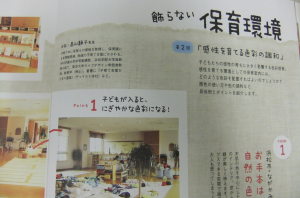
8・9月号は、「子どもだからこそ、本物を」

保育室には、遊びの素材と道具があふれ、子どもたちの遊びが残り、絵本が並べられていれば、それだけでもにぎやかで、壁に飾りは不要なはずです。しかし、どうしても飾りたい場合には、本物の季節飾りや、野菜や果物や木の実などの自然物や、絵画や写真などの本物を飾りましょうと、具体的な提案を行いました。
乳幼児の環境は幼稚でいい、と誰がいつから考えるようになったのか。
色画用紙の壁面飾りから、子どもたちは季節感を本当に感じとっているのか。
色画用紙の飾りは、子どもたちの豊かな感性を本当に育むのか。
幼稚な環境で育った子どもたちは、将来どのようなものを志向するようになるのか。
多忙な保育者が、貴重な時間を使って、飾りに時間を割く必要があるのだろうか。
さまざまな園で先生方から環境構成の意図について話を伺い、認知心理学、環境心理学などを読む中で、これらの疑問が大きくなりました。
壁面製作を環境構成と呼んでいたり、保育者の技術と言われることがあります。しかし、雑誌を真似して壁面を作ることは、子どもの発達や保育の原理などを知らなくてもできます。保育者の技術と呼べる環境構成は、子どもの活動を想定したものであり、その前提に、保育の専門知識があるものを指します。
次回の予定は「自然をとりこむ」。まち中の保育所、駅前保育所などが増え、子どもが育つ環境は貧しくなるばかりです。しかしビルのなかでも、屋外の豊かさの要素を取り込むことはできます。屋外へ出られない、自然物をさわれない地域がある今だからこそ、屋内に自然物と自然の要素を取り込む提案をしたいですね、と神崎さんと話しています。
環境構成の理論については、園と家庭をむすぶ「げんき」エイデル研究所で、連載中です。次号には、保育士のコンピテンシー(力量)リストを掲載します。
コメント
_ 高山静子 ― 2013/08/11 19:06
コメントをありがとうございました。私も日誌苦手でした。経験知が多くて、もっている情報が多すぎると、まとめて短く書く、とか話すことがとても難しいですよね。環境構成は写真で記録が一番!とても効率的に記録をしている園があるので、今度写真を撮ってきてブログに書きますね。ありがとうございます。
