新しい年の始まりです ― 2013/01/01
2013年が始まりました。

初日の出
今年は、静岡へ来てから初めてお正月らしいお休みをすごしています。
今年は、静岡へ来てから初めてお正月らしいお休みをすごしています。

雲のかかった富士山や・・・

夕日に輝く富士山や・・・

元旦の朝日をあびる富士山を見てきました

今年も、皆さんが健康で充実した一年をすごせますように。
そして、皆さんとともに保育の向上に力を注ぐことができますように。
手仕事が得意な先生 ― 2013/01/06
色画用紙はエコではないし、子どもの感性が育つわけでも、活動モデルになるわけでもないし、保育の原理に基づかない根拠のない壁面飾りはもうやめませんか?と、昨年はあちこちでお話ししてきました。
「では、何を壁に飾ったらいいのでしょうか」という質問、よくあります。
保育環境が十分に整っていれば、飾りがなくても殺風景に感じることはあまりないかもしれません。もしも殺風景だと感じる場合は、子どもの遊びの素材を増やしてみるとよいでしょう。
遊びの環境として素材と道具が十分に整ったら、次は季節感や文化を保育室に加えていきましょう。
今日は、手仕事が得意な先生方の作品をご紹介します。
「では、何を壁に飾ったらいいのでしょうか」という質問、よくあります。
保育環境が十分に整っていれば、飾りがなくても殺風景に感じることはあまりないかもしれません。もしも殺風景だと感じる場合は、子どもの遊びの素材を増やしてみるとよいでしょう。
遊びの環境として素材と道具が十分に整ったら、次は季節感や文化を保育室に加えていきましょう。
今日は、手仕事が得意な先生方の作品をご紹介します。

たかくさ保育園さんで見つけたお正月の飾り。

和紙に紙を貼り、グリーンのペンで七草の名前が描いてありました。手作りだそうです。

これも、切り紙を額縁に入れているだけ。思わず真似をしたくなります。

つくりつけの棚があるのはいいなあ、と思ったら・・・

手作りでした。

こちらは大徳保育園さんで発見。
こぐまちゃんや、ぐりとぐらなど、小さなフェルトでつくっておくと、おでかけのときにも、ずっと遊んでいそうです。
言葉遊びの教材としても活用ができそうですね。
フェルトだと子どもが握りやすく、ペープサートや絵カードよりも長持ちするかもしれません。なるほど~。
飾りではないんですが、このクラスには、こんなものや
言葉遊びの教材としても活用ができそうですね。
フェルトだと子どもが握りやすく、ペープサートや絵カードよりも長持ちするかもしれません。なるほど~。
飾りではないんですが、このクラスには、こんなものや

こんなものも発見。

手仕事が上手な先生って、年長児のあこがれの的でしょうね。
日本のワークライフバランス ― 2013/01/10
ある園で、「子どもの健やかな育ちを支えるために長時間保育をやめました」という話を伺いました。
保育者らしい決断だと思いました。子どもの育ちを大切にしていらっしゃるだけではなく、保護者の暮らしも大切にされていらっしゃる園長先生です。
また、別の園では、「家庭に帰すと子どもはテレビに子守をされるだけ。園にいる方が子どもは幸せかも」という話を伺いました。これももっともな話だと思いました。子どもだけで外に遊びに行けるような地域はほとんどありません。
心ある保育者たちは、子どもの育ちを支えたいという思いと、職場や家庭や地域の現状との狭間で苦しんでいます。
保育者らしい決断だと思いました。子どもの育ちを大切にしていらっしゃるだけではなく、保護者の暮らしも大切にされていらっしゃる園長先生です。
また、別の園では、「家庭に帰すと子どもはテレビに子守をされるだけ。園にいる方が子どもは幸せかも」という話を伺いました。これももっともな話だと思いました。子どもだけで外に遊びに行けるような地域はほとんどありません。
心ある保育者たちは、子どもの育ちを支えたいという思いと、職場や家庭や地域の現状との狭間で苦しんでいます。

山口一男、樋口美雄「論争 日本のワーク・ライフ・バランス」日本経済新聞出版社 2008
平成19年(4年前)に行われたシンポジウム『ワーク・ライフ・バランスと男女共同参画』の内容です。ワーク・ライフ・バランスに関連する研究者が8名。各セッションごとに二名が講演、その後互いに意見、それが4セッションという刺激的な内容です。セッションチェアや会場からの質疑と回答もおもしろい。一口にワーク・ライフ・バランスといっても、政策としては多様な方法があることがよくわかります。
いくつか印象に残る言葉を抜書きします。
「私としましては、ワークの中で、あるいはワークの延長線上にどういうふうにライフを考えるかということではなくて、ライフの中でワークを位置づけるということが本来のあり方だという立場をとりたいと思います。ワーク・ライフ・バランスという主張は、どうもワークということを起点にしながらライフを考えているように思えてなりません」
「仕事ワークとそれ以外のバランスというのは、結局は男女両性にとってライフを充実させるためのものであるのですから、いまとられている仕事ワークを中心にしたやり方では、問題の本質にふれません。
(いずれも御船美智子氏:生活経営・生活設計)
「なぜライフからワークを取り出して議論するのかというと、現在の日本では雇用されて働いている人々のライフの現状を考えると、ワークのあり方がライフのあり方を規定する程度が大きい構造になっていることによります。その意味で、ライフのなかのワークが変わらないと、広義のライフを含めたワーク・ライフ・バランス、最近はワーク・ライフ・インテグレーションとも言われますが、それが実現できないと考えているためです」
「私はワーク・ライフ・バランスの説明に際して、仕事以外でやりたいこと、やらなくてはならないことと、仕事の間にコンフリクトがない状態と説明しました。つまり、ワーク・ライフ・バランス支援は、子育て支援に限定されないのです。ですから、仕事以外の生活には、例えば勉強、趣味、遊び、健康維持なども入ります」
(いずれも佐藤博樹氏:人事管理・産業社会学)
「保育サービスを増やすことだとか、専業主婦が集う拠点を作っていくとか、そういう政策については私自身も必要だと思っているのですが、それらの量的な数を増やすという政策ではなくて、その質に対してはいろいろ問題があると思っていて、そこが現在の政策との相違点です」
「子育て支援策について今はもう方向や器はある程度できていますが、その質をどう変えていくかという点では考えるべき課題があると思っています」
「経済的発想によって女性の働く権利だとか、選択の自由、便利な社会というプラスの面があったと思いますけれども、一方で子育てにかかわる時間が減っていくとか、人々のつながりが希薄化して不安になったりですとか、子どもの環境が悪化しているというようなことも起こってきています。ですから精神的な面や自然環境などの議論に、経済学がもっと取り組めないか、また、教育についても労働力というだけではなくて、例えば社会力を高めていく教育というような議論も必要になってくるのではないか、というふうに思います」
(いずれも池本美香氏:保育・教育政策、社会保障制度)
「しばしば、育児休業制度や保育所の整備など両立支援をしてきたのに、結婚出産を経て継続就業する女性はなぜ増えないのかという疑問の声が聞かれます。私は、その背景のひとつには、育児休業、保育所、働き方のいずれも柔軟性が乏しく、①育児休業を利用して育児に専念した後、保育所を活用して長時間就業することと、②育児休業も保育所も利用しないで専業主婦として子育てをすること、これらの二者択一から抜け出せないことがあることがあると思っています」
(権丈英子氏:労働経済学・社会保障論)
日本では男女の賃金格差が高いこと、男性は正規職員が多く女性は少ないこと、正規職員間でも男女差別があることはデータを示されなくても、経験的に理解しているかと思いますが、ここでは男女の賃金格差は統計的差別か、真の差別かなど、おもしろい議論が交わされます。
こういう本を読んでいると、さまざまな人たちの努力によって世の中は変わっていくという実感が湧いてきます。
この本では範囲外でしたが、ワーク・ライフ・バランスを進める企業はどのようなミッションをもっているのか、ワーカホリックを生み出す職場風土、育児休業を取れる職場の風土などを読んでみたいですね。
ワーク・ライフ・バランスを当事者目線で語る本としては、元祖イクメンの渥美由喜さんの本をどうぞ。
渥美由喜「イクメンで行こう!」日本経済新聞出版社、2010
平成19年(4年前)に行われたシンポジウム『ワーク・ライフ・バランスと男女共同参画』の内容です。ワーク・ライフ・バランスに関連する研究者が8名。各セッションごとに二名が講演、その後互いに意見、それが4セッションという刺激的な内容です。セッションチェアや会場からの質疑と回答もおもしろい。一口にワーク・ライフ・バランスといっても、政策としては多様な方法があることがよくわかります。
いくつか印象に残る言葉を抜書きします。
「私としましては、ワークの中で、あるいはワークの延長線上にどういうふうにライフを考えるかということではなくて、ライフの中でワークを位置づけるということが本来のあり方だという立場をとりたいと思います。ワーク・ライフ・バランスという主張は、どうもワークということを起点にしながらライフを考えているように思えてなりません」
「仕事ワークとそれ以外のバランスというのは、結局は男女両性にとってライフを充実させるためのものであるのですから、いまとられている仕事ワークを中心にしたやり方では、問題の本質にふれません。
(いずれも御船美智子氏:生活経営・生活設計)
「なぜライフからワークを取り出して議論するのかというと、現在の日本では雇用されて働いている人々のライフの現状を考えると、ワークのあり方がライフのあり方を規定する程度が大きい構造になっていることによります。その意味で、ライフのなかのワークが変わらないと、広義のライフを含めたワーク・ライフ・バランス、最近はワーク・ライフ・インテグレーションとも言われますが、それが実現できないと考えているためです」
「私はワーク・ライフ・バランスの説明に際して、仕事以外でやりたいこと、やらなくてはならないことと、仕事の間にコンフリクトがない状態と説明しました。つまり、ワーク・ライフ・バランス支援は、子育て支援に限定されないのです。ですから、仕事以外の生活には、例えば勉強、趣味、遊び、健康維持なども入ります」
(いずれも佐藤博樹氏:人事管理・産業社会学)
「保育サービスを増やすことだとか、専業主婦が集う拠点を作っていくとか、そういう政策については私自身も必要だと思っているのですが、それらの量的な数を増やすという政策ではなくて、その質に対してはいろいろ問題があると思っていて、そこが現在の政策との相違点です」
「子育て支援策について今はもう方向や器はある程度できていますが、その質をどう変えていくかという点では考えるべき課題があると思っています」
「経済的発想によって女性の働く権利だとか、選択の自由、便利な社会というプラスの面があったと思いますけれども、一方で子育てにかかわる時間が減っていくとか、人々のつながりが希薄化して不安になったりですとか、子どもの環境が悪化しているというようなことも起こってきています。ですから精神的な面や自然環境などの議論に、経済学がもっと取り組めないか、また、教育についても労働力というだけではなくて、例えば社会力を高めていく教育というような議論も必要になってくるのではないか、というふうに思います」
(いずれも池本美香氏:保育・教育政策、社会保障制度)
「しばしば、育児休業制度や保育所の整備など両立支援をしてきたのに、結婚出産を経て継続就業する女性はなぜ増えないのかという疑問の声が聞かれます。私は、その背景のひとつには、育児休業、保育所、働き方のいずれも柔軟性が乏しく、①育児休業を利用して育児に専念した後、保育所を活用して長時間就業することと、②育児休業も保育所も利用しないで専業主婦として子育てをすること、これらの二者択一から抜け出せないことがあることがあると思っています」
(権丈英子氏:労働経済学・社会保障論)
日本では男女の賃金格差が高いこと、男性は正規職員が多く女性は少ないこと、正規職員間でも男女差別があることはデータを示されなくても、経験的に理解しているかと思いますが、ここでは男女の賃金格差は統計的差別か、真の差別かなど、おもしろい議論が交わされます。
こういう本を読んでいると、さまざまな人たちの努力によって世の中は変わっていくという実感が湧いてきます。
この本では範囲外でしたが、ワーク・ライフ・バランスを進める企業はどのようなミッションをもっているのか、ワーカホリックを生み出す職場風土、育児休業を取れる職場の風土などを読んでみたいですね。
ワーク・ライフ・バランスを当事者目線で語る本としては、元祖イクメンの渥美由喜さんの本をどうぞ。
渥美由喜「イクメンで行こう!」日本経済新聞出版社、2010
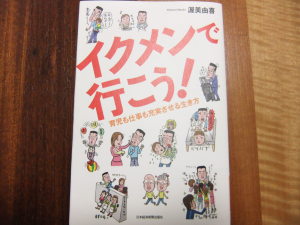
渥美さんとは研究会でご一緒したことがあります。研究会にいつも大きなスーツケースを引っ張ってかけつける渥美さん。(海外出張が多い方だなあ)と思っていましたが、この本を読み、あのスーツケースの中には、紙おむつが入っていたことが判明。渥美パパの家庭と地域と職場での奮闘ぶりに、元気がわいてきます。
しかしながら、暮らしの質を高めるには、育児休業やワーク・ライフ・バランスを進めると同時に、家庭や地域のハードの豊かさを改善することも必要ですね。
たとえ、育児休業を得ても、安心して子どもを育てられる地域がない、というのが日本の多くの地域の現状。
日本のまち(ハード)は、人間に冷たい。まちは車のための場所。人がゆっくり歩ける道路も、人同士が出合える場もありません。(そのために地域子育て支援拠点が必要) 年を重ねて足腰が弱くなれば、斜めの歩道はもう歩けません。家庭は狭く、子どもだけでは外に出られない地域も多い。親子が安心してゆったりと歩ける道も、子どもを安心して遊ばせる公園もない地域が多いのが実情です。分断され、競争をあおられ、長時間働き、商品とサービスの消費でその貧しさを補う大人の暮らし方と価値観が子どもたちの育ちに影響を与えています。
暮らしの質を大切にする価値観が広がり、人を大切にする企業活動・公共政策のあり方を考えていくようになれば、ワーク・ライフ・バランスも進むでしょう。そして、子どもが育つ、子どもを育てる環境として地域社会のつくり直しにも目が向き、ほんとうの意味での子育て支援が広がっていくだろうと思います。
日本の便利で快適な暮らしは、焼野原から働いて働いてご苦労された皆さんの努力の上にあります。
私たち次の世代は、暮らしの「質」を高めることを考え、みんなが幸せに生きられる社会をつくるために努力することが役割なのかもしれません。
新年から環境構成の連載がスタート ― 2013/01/13
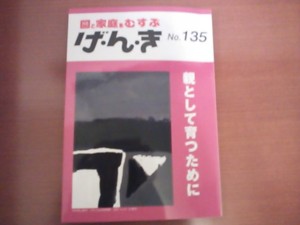
ここ数年、さまざまな園で学びをいただきました。
そして、その多様な保育に共通する実践の骨組みを研究してきました。
このコラムで、先生方へ少しずつ理論をお返ししたいと思っています。
環境を構成する技術は、前提となる専門知識と技術が多い技術です。
平成22年にまとめられた保育士の養成課程の改正では、環境構成の技術を、「保育表現技術」、「乳児保育」、「障がい児保育」で教えることが養成校に通知されました。(保育の内容と方法を教授する科目には、ほかに「保育内容総論」「保育内容」がありますが、残念なことにそれらの科目には示されていません)
今後、各大学・専門学校で「環境構成」を学んだ学生たちが卒業していきます。
日本保育学会や全国保育士養成協議会でも、養成校の環境構成の授業実践が出てくることでしょう。楽しみです。
専門知識という根拠に基づく実践へ。
はいまわる実践から、骨のある実践へ。
保護者に対しても小学校の先生方に対しても、堂々と保育を語ることができる保育者に。
そして本当に誇りと使命感をもった保育の専門職集団へ。
保育のナイチンゲール運動は、はじまったばかりです。
保育園の苦情対応~困難事例 ― 2013/01/19
お茶の水女子大学の青木紀久代先生より、先生が監修された貴重な本を御紹介いただきました。
東京都社会福祉協議会保育部会調査研究委員会による調査結果をまとめたご著書です。
青木紀久代監修 東京都社会福祉協議会保育部会調査研究委員会「保育園における苦情対応~対応困難事例とワーク」東京都社会福祉協議会 2012
東京都社会福祉協議会保育部会調査研究委員会による調査結果をまとめたご著書です。
青木紀久代監修 東京都社会福祉協議会保育部会調査研究委員会「保育園における苦情対応~対応困難事例とワーク」東京都社会福祉協議会 2012

読み込みすぎて、ちょっと本が開いた状態ですみません・・・。

担任の立場から書かれた内容と、園長の立場から書かれた内容があります。

それぞれの事例にワークとワンポイントアドバイスがあります。
対応困難度が大きく、保育者のバーンアウトリスクも高い事例
対応困難度は中程度だが、保育者のバーンアウトリスクは高い事例
対応困難度は大きいが、保育者のバーンアウトは回避されている事例
対応困難度が中程度で、保育者のバーンアウトが回避されている事例の
4つのタイプに分けて事例が説明されます。
たとえば、
子どもの同士のけんか:保護者が賠償金を要求
威圧的な雰囲気に保育者が緊張
「発達障害だなんて・・・」
「うちの子に限って!そんなことはありません!」など、15の事例が紹介されています。
一つひとつの事例は、保護者の様子、対応と職員のサポート、事例のその後と丁寧に説明。
その事例に対して、話し合いができるようにワークが設定されています。
各園で、または各クラスで、日常の研修に活用できる内容です。
また、大学での「保育相談支援の授業」でも活用できそうです。
わたしも読みながら、自分ならどう対応するだろうと考えました。
東京都社会福祉協議会ホームページから購入することができます。
青木先生、ありがとうございました。
対応困難度は中程度だが、保育者のバーンアウトリスクは高い事例
対応困難度は大きいが、保育者のバーンアウトは回避されている事例
対応困難度が中程度で、保育者のバーンアウトが回避されている事例の
4つのタイプに分けて事例が説明されます。
たとえば、
子どもの同士のけんか:保護者が賠償金を要求
威圧的な雰囲気に保育者が緊張
「発達障害だなんて・・・」
「うちの子に限って!そんなことはありません!」など、15の事例が紹介されています。
一つひとつの事例は、保護者の様子、対応と職員のサポート、事例のその後と丁寧に説明。
その事例に対して、話し合いができるようにワークが設定されています。
各園で、または各クラスで、日常の研修に活用できる内容です。
また、大学での「保育相談支援の授業」でも活用できそうです。
わたしも読みながら、自分ならどう対応するだろうと考えました。
東京都社会福祉協議会ホームページから購入することができます。
青木先生、ありがとうございました。
子どもが歩ける道づくり ― 2013/01/30
先日、派手に転んでしまいました。もう酔っ払ってもいないのになんで道で転ぶかな。
腫れた足を冷やしながら、道で転んだぐらいでこんなに痛いのに、鋼鉄の車にはねられた人はどれだけ痛いだろうと想像していました。
浜松では、小学生がヘルメットをかぶっている姿を見かけることがあります。
ある小学校では、下校時に「自分の命は自分で自分で守る」と唱和するそうです。
子どもの命を守るためにとても大事なこと、でも悲しいな。
白い線が引かれただけの歩道を歩く小学生の真横を、大きな鋼鉄の車が通りぬける光景は見ていて苦しい。 悪代官が、そこのけ~っとばかりに、馬に乗って民を蹴散らして走り去るのと同じように見えるのは私だけ?
車中心のまちづくりが当たり前のこの国で、人に優しいまちのハードを提案し広げようとしている人たちがいます。
九州で夢アイディアまちづくりの提案のコンテストを主宰するのは、建築コンサルタンツ九州支部
http://www.jcca.or.jp/kyokai/kyushu/
私も「子どもが育つまち」を書いて応募しました。
国土交通省 国土技術政策総合研究所 道路研究部 道路空間高度化研究室
人が優先のコミュニティゾーンを形成するためのさまざまなアイディアが写真で掲載されています。
「スピード下げろ」とか「制限30」なんて書くよりも、道路にバンプ(盛り上がり)や狭さく(狭い場所)をつくることで、車のスピードを自然に下げることができます。これって保育の環境構成と同じですね。
国土交通省コミュニティ・ゾーン形成事業
コミュニティゾーン形成の必要性と事例が端的にまとめられています。
歩行者の死亡事故の約6割が自宅から500メートル以内とは。ちょっとこわい。
世界交通事故犠牲者の日フォーラムでの津田美知子氏の講演記録
オランダのボンエルフのことを私は千葉大学の木下勇先生のお話で知ったのですが、このキーワードで検索していると、この方の講演記録が出てきました。公共空間、まちのハードは、人の行動に影響を与えるにも関わらず、とにかく情報不足です。
腫れた足を冷やしながら、道で転んだぐらいでこんなに痛いのに、鋼鉄の車にはねられた人はどれだけ痛いだろうと想像していました。
浜松では、小学生がヘルメットをかぶっている姿を見かけることがあります。
ある小学校では、下校時に「自分の命は自分で自分で守る」と唱和するそうです。
子どもの命を守るためにとても大事なこと、でも悲しいな。
白い線が引かれただけの歩道を歩く小学生の真横を、大きな鋼鉄の車が通りぬける光景は見ていて苦しい。 悪代官が、そこのけ~っとばかりに、馬に乗って民を蹴散らして走り去るのと同じように見えるのは私だけ?
車中心のまちづくりが当たり前のこの国で、人に優しいまちのハードを提案し広げようとしている人たちがいます。
九州で夢アイディアまちづくりの提案のコンテストを主宰するのは、建築コンサルタンツ九州支部
http://www.jcca.or.jp/kyokai/kyushu/
私も「子どもが育つまち」を書いて応募しました。
国土交通省 国土技術政策総合研究所 道路研究部 道路空間高度化研究室
人が優先のコミュニティゾーンを形成するためのさまざまなアイディアが写真で掲載されています。
「スピード下げろ」とか「制限30」なんて書くよりも、道路にバンプ(盛り上がり)や狭さく(狭い場所)をつくることで、車のスピードを自然に下げることができます。これって保育の環境構成と同じですね。
国土交通省コミュニティ・ゾーン形成事業
コミュニティゾーン形成の必要性と事例が端的にまとめられています。
歩行者の死亡事故の約6割が自宅から500メートル以内とは。ちょっとこわい。
世界交通事故犠牲者の日フォーラムでの津田美知子氏の講演記録
オランダのボンエルフのことを私は千葉大学の木下勇先生のお話で知ったのですが、このキーワードで検索していると、この方の講演記録が出てきました。公共空間、まちのハードは、人の行動に影響を与えるにも関わらず、とにかく情報不足です。
我が国の子どもの成育環境の改善にむけて-「成育空間の課題と提言(2008)」の検証と新たな提案
日本学術会議 心理学・教育学委員会・臨床医学委員会・健康・生活科学委員会・環境学委員会・土木工学・建築学委員会合同 子どもの成育環境分科会 平成23年
「ほんとうの豊かさは、ほのか、かすか、わずかのなかに」という話は、ガイヤシンフォニーの中だったか。
もっと速く、もっと便利にの大規模公共事業から、身近な地域の暮らしの質を高めるための公共事業へ。
年を重ねても、子どもの命を守るための歩道の確保や、子どもを健やかに育てるための遊び場の確保を最優先できる市民でありたいものです。
と書いていたら、スローライフの本たちを読みたくなってしまった。
転んで今足をひきずっているので、歩き方はスローです。
って別に、このブログを書くために転んだわけではありません・・・。

安全な顔をした危険な場所。アフォーダンスが不自然な人工物。
