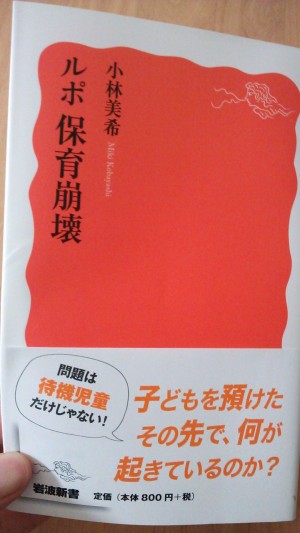「はう運動遊び」の今井寿美枝先生に ― 2015/05/08
チャイルドハウスゆうゆうの施設長である今井寿美枝先生に、ゼミで「はう運動遊び」を教えていただきました。
「はう運動遊び」をテーマに研究する学生のため、そして今井先生の遊びを通して指導する雰囲気を、学生たちに直接味わってほしいと、先生にお願いして来て大学まで講義に来ていただきました。

先生は、この2冊の著者でいらっしゃいます。

今井寿美枝、『はう運動あそび』で育つ子どもたち、2014、 丸山美和子・今井寿美枝、生活とあそびで育つ子どもたち、2010、いずれも大月書店。
月に何十冊も本を読むけれども、めったに本を買わない私が、「これは絶対お薦めです」と、先生方に薦めている保育の本です。河添邦俊先生に生活リズムを学んだ保育者の皆さんには、なるほど河添理論がこのような実践になったのか、と納得していただけると思います。

本に紹介されている遊びを実際にみんなで体験してみました。私もやりたい、でも写真も撮らなきゃ…。写真左上が今井先生です。動きがお若い!

大人でもキャーキャー大騒ぎになります。子どもたちと一緒だと、どれほど楽しいでしょう。
最後は、「だいだいだーいすき」を歌って終わりました。この歌は子育て支援や懇談会で使いたいですね。
なぜ、子どもたちが劇的に変わるのか、直接先生のご指導を受けてわかりました。
それは、「はう運動遊び」が、「遊び」だったから。本当に楽しいのです。先生のはじけるような笑顔と遊び心で、思わず子どもがやってみたい!と動いてしまうしかけがあり、やってみると面白い。
発達に合った動きが選ばれていて、オリジナルのうたも安定したリズムがあり模倣しやすい。そして何より人と関わる喜びが遊びのなかに組み込まれています。子どもは人間のなかで人に育つ、発達の本質です。みんなと一緒だと楽しいなあ、先生だ~いすき、子どもがそう感じられる遊びでした。
今井先生の遊びは、まず子どもへの熱い思いがあり、その思いを理論に基づいて活動にし、目の前の子どもに合わせて自在に応用する実践でした。今井先生には理論という確かな根拠がありました。理論という背骨のある専門家は現場に合わせて自由自在に動き回ることができる、そして人に説明できる・・・やはり学びは大切です。
雑巾も、腕の力が弱い子どもの場合には乾いた雑巾を使います。ここでも発達に則した教材選択が光ります。

気づきが多すぎて書きたいことだらけですが、私のブログより、ぜひ今井先生の本をご覧いただき、研修会に今井先生をお呼びいただければと思います。
今井寿美枝先生、貴重なお時間をいただいて後進のご指導をいただきまして、ありがとうございました。
乳幼児期の教育を伝えるお便り ― 2015/05/14
「幼児教育」といえば、多くの人が思い浮かべるのが、ミニ小学校のような机に座った幼児教室。
子どもを机に座らせて何かをさせている園は幼児教育をやっていて、遊ばせている園は幼児教育をやっていないという誤解もあったりします。
「幼稚園教育要領」には、幼児の自発的な活動としての遊びは重要な学習であると示されています。幼児期の教育は遊びを通して行うことを理解していることが、幼児教育を学んだ証拠です。
保育では、ただ自由に子どもたちを遊ばせているわけではなく、幼児教育として意図をもって環境を構成し、子どもの文化を選択し、遊びを通して子どもが学びを得るように配慮しています。つまり毎日が総合学習。しかしそれをわかりやすく保護者に伝えることはなかなか難しいものです。
そこで、保護者向けのお便りの下書きを書いて、「どなたか、イラストや文章を完成させて下さいませんか?」と、ホームページに下書きをアップしていました。有り難いことにグレース保育園の先生方がお便りを完成して送ってくださったのです! 以下のホームページで完成バージョンのお便りファイルをダウンロードできます。
保育の専門性を高めるページ:ダウンロード専用ページ
保育の専門性を高めるページ:ダウンロード専用ページ
「0歳児の効果的な教育とは」、「1、2歳児の効果的な教育とは」、「幼児期の効果的な教育とは」と、保護者のニーズに合わせてタイトルをつけました。白黒コピーで印刷してもわかりやすい編集です。A4一枚に印刷できます。

「必要感のある学びが幼児を伸ばします」、「保育園は幼児教育を行っています」、「幼児教育では、環境に教育的意図を埋め込んでいます」など、保護者の不安に応え、幼児期の教育方法を解説したお便りもあります。


園内研修の資料として、小・中学校の先生方に幼児期の教育を説明するときの資料にも、学童期との教育内容の連続性を話し合う資料としても、ご活用いただけるかと思います。
私の推定4歳と言われるイラストがステキなイラストに変身。感激です。

グレース保育園の甲斐先生、末元先生、廣次先生、ありがとうございました!!
ブログがきっかけとなった出会いに心より感謝しています。
こどもの環境づくり公開研究会第二弾 ― 2015/05/21
日本建築学会の福祉施設小委員会こども施設環境情報収集ワーキンググループ主催の公開研究会第二弾が、浜松市のながかみ保育園で開催されます。
6月5日は、児童デイ併設のながかみ保育園、6月6日は、今年の4月に開園したばかりの高齢者施設と併設されたながかみ中央保育園の見学会もあります。

開園する前のながかみ保育園を見学させていただきました。ホールが広い!!今回の設計にも、保育者の知恵が随所に埋め込まれていました。

こちらは児童デイが併設されたながかみ保育園です。
| 2015/06/05~06 | 公開研究会「こどもの環境づくり ―その意義と実践」(第二回) | 浜松・ながかみ中央保育園 |
こどものための保育施設を取り巻く状況は変化している。とりわけ,幼稚園・保育所・準認可保育所の従来の区切りを変え,保護者の就労状況等によらずこどもたちがそれぞれのニーズに合った保育を受けることができるよう制度を改革する,いわゆる“幼保の一元化” の本格実施を2015 年4 月に迎えた。
このような時節において,こどもたちの成長・発達を助ける保育施設やその環境のあり方の本質に立ち返り,「何を目指して」「どのように」環境をつくっていくかを改めて議論し,保育環境に関わる多様な主体で共有することが求め
られる。こうした視座に立ち,当小委員会では様々な事例の視察や現場での議論を重ね,2014 年夏にその成果を発信すべく『こどもの環境づくり事典』を編纂した。
2015 年2 月に開催された第一回公開研究会では,この本の出版記念も兼ねて,保育・幼児教育の現場の方,設計者,保育環境の研究者(保育,建築)のそれぞれの立場から,保育施設における環境づくりの意義と実践への考えを語り,相互理解の上に立つ環境の向上に資する議論を行った。本,第二回公開研究会では,新たな登壇者をお迎えして保育施設における環境づくりについてお話をいただき,保育と建築,実践と研究の,多角的な視点から議論を発展させる。
このような時節において,こどもたちの成長・発達を助ける保育施設やその環境のあり方の本質に立ち返り,「何を目指して」「どのように」環境をつくっていくかを改めて議論し,保育環境に関わる多様な主体で共有することが求め
られる。こうした視座に立ち,当小委員会では様々な事例の視察や現場での議論を重ね,2014 年夏にその成果を発信すべく『こどもの環境づくり事典』を編纂した。
2015 年2 月に開催された第一回公開研究会では,この本の出版記念も兼ねて,保育・幼児教育の現場の方,設計者,保育環境の研究者(保育,建築)のそれぞれの立場から,保育施設における環境づくりの意義と実践への考えを語り,相互理解の上に立つ環境の向上に資する議論を行った。本,第二回公開研究会では,新たな登壇者をお迎えして保育施設における環境づくりについてお話をいただき,保育と建築,実践と研究の,多角的な視点から議論を発展させる。
日時・会場:
6月5日(金)
10 時~ 16 時:ながかみ保育園,
同分園(児童発達支援事業所ながかみ)見学会
*10 時,11 時,13 時に分園で見学参加受付
6月6日(土)
10 時~ 12 時:ながかみ中央保育園見学会
13 時~16 時:公開研究会(於 ながかみ中央保育園ホール)
公開研究会プログラム(予定) :
1)登壇者紹介:山田あすか(WG 主査/司会:東京電機大学)
2)講演(各20 分):
村上 博文(富士常葉大学)
「趣旨説明:今日のこども施設をめぐって」
安井聡太郎(子ども建築デザインネットワーク)
「設計者の立場から」
野村 弘子(社会福祉法人七恵会ながかみ保育園)
「保育の現場から」
高山 静子(東洋大学)
「保育研究者の立場から」
藤田 大輔(岐阜工業高等専門学校)
「こどもの環境づくりのために
~設計・保育研究・保育現場をつなぐ」
3)ディスカッション
4)まとめ:橘弘志(実践女子大学)
6月5日(金)
10 時~ 16 時:ながかみ保育園,
同分園(児童発達支援事業所ながかみ)見学会
*10 時,11 時,13 時に分園で見学参加受付
6月6日(土)
10 時~ 12 時:ながかみ中央保育園見学会
13 時~16 時:公開研究会(於 ながかみ中央保育園ホール)
公開研究会プログラム(予定) :
1)登壇者紹介:山田あすか(WG 主査/司会:東京電機大学)
2)講演(各20 分):
村上 博文(富士常葉大学)
「趣旨説明:今日のこども施設をめぐって」
安井聡太郎(子ども建築デザインネットワーク)
「設計者の立場から」
野村 弘子(社会福祉法人七恵会ながかみ保育園)
「保育の現場から」
高山 静子(東洋大学)
「保育研究者の立場から」
藤田 大輔(岐阜工業高等専門学校)
「こどもの環境づくりのために
~設計・保育研究・保育現場をつなぐ」
3)ディスカッション
4)まとめ:橘弘志(実践女子大学)
参加費: 会員1,500 円、一般2,000 円、学生600 円 (資料代含む/当日会場払い)
定 員: 80 名(申込み先着順)
申し込み方法:
事前申し込みが必要です。下記の内容を通信欄に明記し,
【5/29】までに学会HP からお申し込みいただきます。
<https://www.aij.or.jp/index/?se=sho&id=1127>
期限後またはテクニカルトラブルの際は下記のお問い合わせメールアドレスまでご連絡ください。
①6月5日(金)ながかみ保育園見学会参加の有無
*参加の場合,参加開始時刻を10 時・11 時・13 時から選んで記載してください
②6月6日(土)ながかみ中央保育園見学会参加の有無
③連絡先電話番号
*直前・当日の急な予定変更や確認等,必要な時のみに 用います
④連絡先E-mail アドレス
*見学会の集合場所等詳細は,連絡先E-mail アドレスに お送りいたします
お問い合わせ:
定 員: 80 名(申込み先着順)
申し込み方法:
事前申し込みが必要です。下記の内容を通信欄に明記し,
【5/29】までに学会HP からお申し込みいただきます。
<https://www.aij.or.jp/index/?se=sho&id=1127>
期限後またはテクニカルトラブルの際は下記のお問い合わせメールアドレスまでご連絡ください。
①6月5日(金)ながかみ保育園見学会参加の有無
*参加の場合,参加開始時刻を10 時・11 時・13 時から選んで記載してください
②6月6日(土)ながかみ中央保育園見学会参加の有無
③連絡先電話番号
*直前・当日の急な予定変更や確認等,必要な時のみに 用います
④連絡先E-mail アドレス
*見学会の集合場所等詳細は,連絡先E-mail アドレスに お送りいたします
お問い合わせ: