通信の工夫あれこれ ― 2010/05/01
保育者は、保育の専門家ですから、保護者よりも知識や経験があるのは当たり前。知識や経験があると、初めて子育てする保護者に対して、ついあれこれとアドバイスしたくなります。
しかし、気づいたことをあれこれアドバイスしていると逆効果の場合もあります。
 「育つ・つながる子育て支援」より、イラスト:大枝桂子
「育つ・つながる子育て支援」より、イラスト:大枝桂子
毎日夜更かししてつらそうな子どもさんに気づいても、その親御さんに、「もっと早く寝かせて下さい」なんて直接的に言うだけでは芸がない。夜更かししている子どもは、クラスにもたくさんいて、(10時に寝るなんてみんな普通なのに、なんでうちだけ?)と思ってしまうかもしれません。
保育者の常識は、一般の親御さんの非常識だったりします。
そこで、すべての親御さん向けに通信を書くという手段があります。読むという行為は、主体的な行動です。また夫や家族と一緒に見ることができるため、直接先生に言われるよりも、情報を受け取めやすくなります。
夜更かしだって、図にしてしまうとわかりやすい。
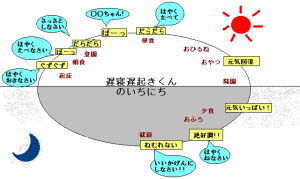
通信も、子どもへの声かけと同じ。
肯定的に、楽しく、わかりやすく。
「○○して下さい」
「○○が大切です」よりも、
「○○すると、こんなに楽」
「○○すると、こんなにいいことがある」という
伝え方ができるといいですね。
子育て支援の通信「ひだまり通信」ではこんな感じ。 「子どもの行動の解説」や「大人のかかわり方」を できるだけ具体的に書くようにしています。
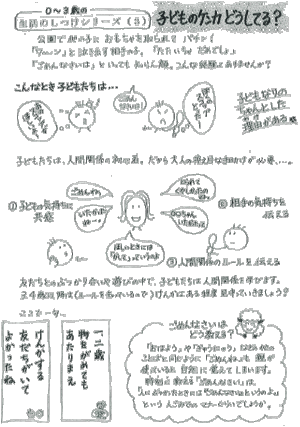
イラストの分量を多くして、難しい単語や漢字はできるだけ使わず、情報のバリアフリーを心がけます。
通信やノートでは、とくに「!」の使い方には注意が必要。
「!」をつけると押し付けがましさが増し、文の表情が恐くなります。
「必ず持ってきて下さい!」
「夜更かしをさせていませんか!」
「!」をつける場合は、ポジティブな言葉につけましょう。
「絶対に大丈夫です!」
「お母さんは本当にがんばっていらっしゃいます!」 のように。
顔に表情があるように、文章にも表情があります。 にっこりと笑った楽しい通信を書いてみましょう。
しかし、気づいたことをあれこれアドバイスしていると逆効果の場合もあります。

毎日夜更かししてつらそうな子どもさんに気づいても、その親御さんに、「もっと早く寝かせて下さい」なんて直接的に言うだけでは芸がない。夜更かししている子どもは、クラスにもたくさんいて、(10時に寝るなんてみんな普通なのに、なんでうちだけ?)と思ってしまうかもしれません。
保育者の常識は、一般の親御さんの非常識だったりします。
そこで、すべての親御さん向けに通信を書くという手段があります。読むという行為は、主体的な行動です。また夫や家族と一緒に見ることができるため、直接先生に言われるよりも、情報を受け取めやすくなります。
夜更かしだって、図にしてしまうとわかりやすい。
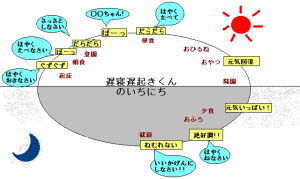
通信も、子どもへの声かけと同じ。
肯定的に、楽しく、わかりやすく。
「○○して下さい」
「○○が大切です」よりも、
「○○すると、こんなに楽」
「○○すると、こんなにいいことがある」という
伝え方ができるといいですね。
子育て支援の通信「ひだまり通信」ではこんな感じ。 「子どもの行動の解説」や「大人のかかわり方」を できるだけ具体的に書くようにしています。
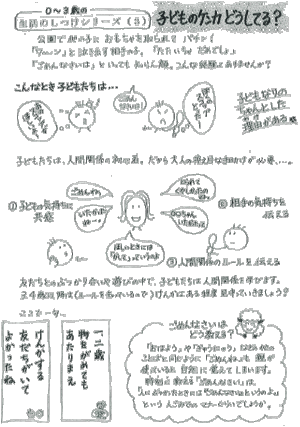
イラストの分量を多くして、難しい単語や漢字はできるだけ使わず、情報のバリアフリーを心がけます。
通信やノートでは、とくに「!」の使い方には注意が必要。
「!」をつけると押し付けがましさが増し、文の表情が恐くなります。
「必ず持ってきて下さい!」
「夜更かしをさせていませんか!」
「!」をつける場合は、ポジティブな言葉につけましょう。
「絶対に大丈夫です!」
「お母さんは本当にがんばっていらっしゃいます!」 のように。
顔に表情があるように、文章にも表情があります。 にっこりと笑った楽しい通信を書いてみましょう。
