ごっこ遊びの環境を学ぶ ― 2014/06/01
ゼミで、お家ごっこの環境をつくり、近隣の園の子どもたちに遊びに来てもらいました。
場所は学内の保育実習室。3歳児向けのごっこ遊び空間を、3か所作りました。
まず環境構成の原則的な理論を学習した後に、学生たちで話し合って、充実したごっこ遊びができる空間、集団での保育に合わない素材や道具が置かれた空間、ごっこ遊びが広がらないように工夫した残念な空間の3つを作りました。学生たちがごっこ遊びが広がるように必要な素材や道具などを考えて小物を作ったり購入したりしました。最後に時間の関係で、私が解説しながら3つの空間を修正しました。

手前右、右奥、左奥の三カ所に作りました。中央のじゅうたんは他の授業で使用しているものです。
遊びが広がらない空間として、私がケースの中にプラスチックの野菜とお皿と人形を混ぜると、「いやだ~」「人形がかわいそう」「こんなんじゃ遊べない」と学生たちから一斉に叫び声が。一度玩具が棚に並んだ状態に慣れてしまうと、箱の中に玩具を入れることには耐えられなくなるようです。

遊びが広がりにくい空間では、ケースに玩具を入れます。ケースの色も、ごっこ遊びのイメージが広がりにくい濃いブルーの色です。子どもを引き付けるカラフルなクッションと、ごっこ遊びと関係のない壁面飾りを加えて、子どものイメージを広がりにくくしました。担当する学生は、子どもの注意を引くキャラクターのエプロンをつけます。
ちょっと残念な空間は物の質と量に問題があります。素材や道具は置かれているけれども、子どもの発達に合わない大きさであったり、具材も集団にふさわしい量が準備されていない空間を準備しました。

ままごと道具は、すべて木製の小さなもの。レンジ台も小さい。具材はテーブル上のボール一つ分。人形は世話をしにくい大きさと柔らかさの人形を並べました。窓の飾りは、学生たちが「こんなにさびしい空間では子どもが誰も来てくれない」と貼ったものです。
ごっこ遊びが広がる空間には、素材と道具を準備しました。具材にはチェーンリングや花はじき、フェルトで作った具材を準備し、手前側に人形がいます。レンジ台の高さが年長向けですがこれは妥協、作業台もないため机で代用しました。仕事をする上で現実的制約は付き物なので、妥協も学生に学習してほしいことの一つです。

最初の15分間は子どもと関わらないというルールを設けて、観察に徹することにしました。
子どもたちがやってくると、全員が素材と道具が充実した空間で遊びはじめてしまい、その後、他の空間へ誘うという結果になりました。後から考えるとああすればよかった、こうすればよかったと課題だらけでしたが、学生たちは、子どもが素材を見立てて遊ぶ姿と、手と道具を使うことに専心する姿を見ることができ、その他の空間と比較ができたため、学びの内容としてはよかったと満足することにしました。
講義で聞くことと、実際に子どもの姿を見ることには大きな差があります。学生たちは、保育者が選んで置いた物によって、子どもの遊びが変わることを実感できたようでした。保育実習室があることで、子どもの遊びや行動を予測しながら、何度も空間を作りかえることができます。学生たちが実際に何度も棚やじゅうたんを動かし、遊びの素材を並べ替えることで、「環境は変えることができる」ことを体に染みつけてほしいと思いました。
学生は、子どもと関わることを望みますが、子どもと保育者の援助を理解する上では、「子どもと環境とのかかわりをじっくりとみる体験」が養成では非常に重要だと感じた次第です。ご協力を賜った先生方、大変にありがとうございました。
今回は家庭ごっこでしたが、言葉遊びの環境、造形表現の環境、運動遊びの環境についても試してみたいものです。環境構成技術を獲得する授業について試行錯誤中。
園に置いておきたい本~遊びの素材と道具 ― 2014/06/09
子どもを遊んであげる先生と、子どもが遊べるように援助をする先生がいるように、玩具にも、子どもを遊んでくれるおもちゃと、子ども自身が遊びをつくりだす素材と道具があります。
子どもは好奇心が強いため、刺激で子どもを引き付けるようなおもちゃにはすぐに飽きてしまいます。
子どもたちが遊びで必要としているものは、想像力や思考力を付け加えて遊びを作りだすことができるシンプルなもの。子どもが草、土、木などの自然物では飽きずに遊ぶのは、自然物は応答性が高く、想像や思考をつけ加える余地があり、可塑性が高くて繰り返しができるために、子ども自身が遊びをひろげることができるからです。
保育室内には土や砂を持ち込むことはできませんが、自然物のような性質をもった遊びの素材と道具を揃えると、子どもは飽きずに遊び込むことができます。
日本の集団保育は、半世紀以上の歴史があります。各園で「どんなおもちゃを準備しよう」と、一から考えるのはもったいない。様々な参考資料を見ながら、他の人の実践と知恵を活用して、より目の前の子どもに合ったものを作ったり選ぶ方が賢明です。
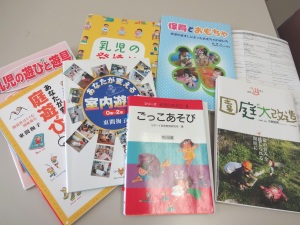
園と家庭をつなぐ「げんき」編集部、乳児の発達と保育、エイデル研究所、2011
上記の改訂版
コダーイ芸術教育研究所、ごっこ遊び、明治図書、1992
渡辺幸子、乳児の遊びと遊具、明治図書、2008
東間 掬子、あなたが変える室内遊び、サンパティックカフェ、2004
東間 掬子、あなたが変える庭遊び、サンパティックカフェ、2000
小泉昭男、自然と遊ぼう園庭大改造~命の営みを感じられる園庭に、ひとなる書房、2011
他にもいろいろと手作りの玩具の本も出ていますが、本はあくまでも参考に。
手作りであっても「子どもを遊んでくれるおもちゃ」と、「子どもが遊びを創りだせるおもちゃ」がありますので、選んで作りたいものです。手作りをする場合には、保育室全体の刺激量を考えて色柄と素材を選びたいものです。
自然のものと自然ではないもの ― 2014/06/16
(公財)日本生態系協会から、「こども環境管理士資格試験の案内」が送られてきました。
後援には保育団体がずらりと並んでいます。
ホームページを読んでいると、「自然のもの」と「自然ではないもの」を、きちんと区別しましょうとの一文が。
自然のものとは、
シジュウカラ、ツバメ、アマガエル、ニホントカゲ、アゲハチョウ、アブラゼミ、ヤマザクラ、スギナ、カタバミなど、もともと地域にいるさまざまな野生の生きものを指すそうです。
自然ではないものとは、
チャボ、あひる、いえうさぎやぎ、金魚、ひまわり、チューリップ、稲、さつまいも、桜(ソメイヨシノ)、ウシガエル、アメリカザリガニ、シロツメクサ、レンゲなど、飼育・愛玩動物、園芸種・農作物、外来種は、自然ではないものになるそうです。
なるほどねぇ。生態系の視点から考えると、こういう区別が必要になるのだなあと思いました。
今、運動場のような園庭を、自然豊かな園庭に変えている園が増えていますが、この視点を持っているとよいかもしれません。園庭にビオトープをつくるときには、この自然のもの:自然ではないものの区別が生きるでしょう。しかし、子どもが人間の暮らしを学ぶためには、稲や野菜を育て家畜を飼う経験が必要かもしれません。
自然を人間の暮らしに合わせてつくりかえた里山的な自然で育った私には、自然のものだけの地域環境がうまく想像できません。これらの知識をどのように実践に活かしているのか、ぜひ園に伺って学んできたいと思いました。
公益財団法人 日本生態系協会

私の大好きな景色は、「自然ではない」植栽ばかりです。
無料のe-Learningで園内研修 ― 2014/06/21
テレビやビデオなど映像系に映るのが大の苦手な私ですが、今、幼児教育を保護者に説明することができる保育者が増える必要があると考え、放送番組の仕事をお引き受けしました。
日本保育協会さんのホームページへアクセスして、

この右側に見える 「保育e-Learning(保育者の無料の保育研修サイト)」というボタンをクリックすると

小西さんの素敵な写真が出迎えてくれます。

「研修内容を探す」をクリックすると、様々な研修テーマの一覧が出てきます。
登録は簡単。かつ無料です。園にプロジェクターがあれば、職員全員で同じ研修を受けることができます。研修内容は、20分から40分ぐらい。見て話し合うのにぴったりの長さです。
講師は、網野武博、井桁容子、遠藤利彦、大方美香、岡健、汐見稔幸、橋本真紀、平田智久、増田まゆみ、山中龍宏等、様々な領域の専門家が務めています(敬称略、アイウエオ順)。
私が担当した番組は、「保育の原理」です。なぜ幼児期の教育方法は遊びなのか、保育者は何を根拠にして保育内容を選ぶのかなど、保育の原理原則を再確認する内容です。保育者が自分の言葉で語ることができるように、「はい、ここまでの内容をまとめて二人組で話してみましょう」という、いつもの演習も入っています。何度も相手を変えて練習をしたり、相手役の人が指導主事や保護者に扮して質問や意見を述べるロールプレイを行うやり方もあります。この演習で、自分の主観から一歩離れ、根拠に基づいて話をするトレーニングができます。思い込みを排し、内容をありのままに受け取ってまとめる練習は、子どもの保育や保護者の支援にもいきるでしょう。
保育原理のアップは7月頃だそうです。
画面に出る内容は、配布資料として印刷もできます。ご活用下さい。
