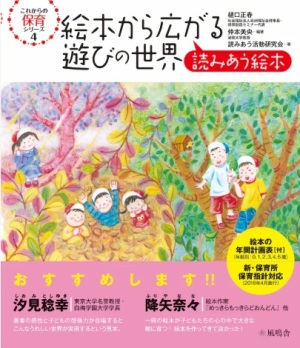高温化と園庭の環境 ― 2025/05/25
5月ですが、すでに真夏のような暑さの日がありますね。
先日伺った園では、もう園庭中にタープが張られていました。
暑い日も寒い日も、子どもたちと一緒に遊ぶ先生方、本当にお疲れ様です。
真夏になると高温注意情報や、熱中症特別警戒アラートが発表されます。
しかし警報は出ていなくても、5月から熱中症の救急搬送は起きています。
5月であっても水分補給や活動内容などに留意したいですね。
気候が変化しているのに例年通りの保育を行う、が一番危険。
とくに私立の保育園やこども園では、
気温に合わせて、例年より早く園庭にタープを張る。
気温に合わせて、水遊びを行う。
室内、園庭では、例年より早く水分補給コーナーをつくる。
例年通りの園庭・ホールでの運動会の練習はさける。
気温や湿度が高い日にホールで例年通りの活動をしない。
など、子どもの命を守る柔軟な対応が多く見られます。
園庭にも工夫がほどこされています。

園庭を森にしたながかみ保育園さんの園庭
高温化と大気汚染から子どもを守るために、
今、運動場のような園庭から、
森のような園庭へと改善している園が増えています。
園庭に木陰がもっとほしい。
落ち葉プールができるほど木を増やしたい。
チョウや虫や鳥が来る園庭をつくりたい。
そんな願いを実現するための補助金もあります。
今、自然はある意味ぜいたく品と言えます。
子どもが歩いていける範囲に森があるのはごく一部の地域だけです。
園長先生か市長さんは、どんな地域にも新しい森をつくることができますね。
乳幼児期の運動は、食事や睡眠と同じ ― 2025/05/18
最近2つの園の保育者から、「公園が危なくて子どもを遊ばせることができない」という話を聞きました。

車道へ子どもが飛び出すことが予測される公園の例
共通していたのは公園の隣が道路なのに子どもが飛び出さない仕組みがないこと。
それでは保育者も保護者も安心して子どもを見守ることができないでしょう。
こういう話をすると、「親や先生がちゃんと子どもを見るべきだ」と言う人がいますが、
元々人間には、複数の子どもを同時にどこで誰が何をしているかを見る注意力は備わっていません。
10人、20人の子どもの行動を一人で見守ることは元々無理なのです。
そのため幼稚園や保育園では、門に鍵を二重にかけて子どもが道路に飛び出さない仕組みがあります。
車道に飛び出す公園はプールと同じ。人の注意に頼って安全を守ることには限界があります。
園庭が狭く、公園でも遊ばせることが危険となると、子どもの育ちには不利益が生じます。
乳幼児にとって、体を動かすことは発達に不可欠であり、
食事や睡眠と同じように毎日欠かすことができない生理的欲求です。
「昨日は公園で走り回ったから、今日は静かにすごそうね」なんてできません。
乳幼児期の子どもに、「じっとしていなさい」と言うことは、
「あなたは脳を発達させていけません」
「あなたは能力を獲得してはいけません」
と言うことと同じです。
「あなたは脳を発達させていけません」
「あなたは能力を獲得してはいけません」
と言うことと同じです。
乳幼児は動くことによって新しい能力を獲得します。
1歳の子どもは高いところに繰り返し登っては、高いところに登る能力を獲得し、
2歳の子どもは走り回って、走る能力を獲得します。
大人は登る能力を獲得しているため、高いところを見つけても、いちいち登りません。
人間の子どもは、複雑な脳のシステムをつくるために、起きている間中、活動を欲しています。
昔は「放っておいても子は育つ」と言われ、子どもが動き回れる地域がありました。
しかし今地域は車中心のまちづくりであり、
多くの親は子どもを遊ばせるためだけに公園へ連れていきます。
まちのハードは、子どもと大人、両方の行動に影響を与えています。
まちと子育てについてはまたつぶやきたいと思います。
子どもの経験と絵本 ― 2025/05/11
こどものとも社の丸山さんから復刊した絵本を教えていただきました。

石川県輪島の朝市を描いた1980年に刊行された絵本だそうです。
海でとれたもの、山でとれたものを持ち寄る市場。
ある園長先生が、「祖母の店が描かれているんです」と教えてくれました。
市場のにぎやかさを知る子どもたちにも、スーパーしか知らない子どもたちにも読みたい絵本です。
能登半島地震の復興への願いを込めて収益は寄付されているそうです。
「エスカレーターとエレベーター(かがくのとも)」福音館書店、2023
 こちらは、都会の子どもにとってなじみ深い経験を描いた科学絵本です。
こちらは、都会の子どもにとってなじみ深い経験を描いた科学絵本です。

エスカレーターはある子どもにとっては身近ですが、ある子どもにとっては、ものがたりのような世界かもしれません。
絵本やごっこ遊びの環境は、子どもたちの地域や家庭での経験もふまえて選びます。
たとえば下の絵本はサッカースタジアムが身近な園やサッカー大会などに出る園で、置いておきたい絵本です。
こちらは月刊絵本のため、駒込の福音館書店本社まで買いに行きました。

福音館書店のかがくのともシリーズは、綿密な取材と時間をかけた作成が知られていますが、どのスタジアムを取材したのかを想像するのも楽しいですね。(赤いユニフォームです)

こちらも月間絵本です。こちらも綿密な取材を感じる本です。
保育者は、モンシロチョウが飛び交う頃になるとチョウの絵本を置き、園庭にテントウムシが出てくと、テントウムシの絵本を置きます。その園で子どもが出会える花や虫の絵本は、担任が変わっても必ず揃えておきたいものです。
季節と、地域と、子どもの経験に合わせて絵本の入れ替えを行う保育者の皆さん、いつもお疲れ様です!
*現在福音館書店の販売コーナーでは月間絵本が販売されていますが、「サッカースタジアム」や「テントウムシのいちねん」は、ない可能性もありますのでご注意ください。
人形の選び方 ― 2025/05/04
「環境のアドバイスを下さい」と園へ呼ばれて、園で必ず見るポイントの一つに「人形」があります。
人形選びには、発達の理解と、玩具選びの原則の理解が見えやすいからなんです。
玩具選びの原則は、「子どもの姿に合わせて玩具を選ぶ」です。
園で人形を選ぶポイントには
1.大きさ
2.硬さ
3.手足の動きやすさ
4.精巧さ
5.表情
6.耐久性
2.硬さ
3.手足の動きやすさ
4.精巧さ
5.表情
6.耐久性
があります。
その年齢の子どもが扱いやすいかどうかは、大きさ、硬さ、手足の動きやすさによって変わります。
たとえば1歳児クラスに小さくて手足が動く人形を置くと、子どもが抱いたり寝かしつけたりしにくくなります。1歳児クラスには、子どもが抱きやすい大きさで綿の詰まった人形を置くと、子どもは人形を抱いたりおんぶしたり、ミルクを飲ませたりの世話がしやすくなります。

写真は手作りのお人形です。綿をしっかりめに入れると1歳児、2歳児に扱いやすくなります。
輸入玩具の定番、くまちゃん・うさちゃんも、大きさを選ぶと1,2歳児には扱いやすいですね。
1,2歳児クラスは、一人遊び、平行遊びの時期です。同じが嬉しい時期のため、同じ人形を複数体置くようにします。
洋服の着替えをさせることができる年齢になると、手足が動く人形だと遊びが広がるでしょう。
本物らしさを求める5歳児以降には、指がある、鼻や耳があるなどの精巧な人形があるとお医者さんごっこ等の遊びが広がりやすくなります。

集団保育の玩具選びでは、耐久性も重要です。
保育カタログには、大きすぎる人形や耐久性の低い人形もありますのでよく確認して購入しましょう。
表情については以前書いたので以下をご覧ください。
ごっこ遊びの人形は、以下にも写真を掲載しています。
ちなみにぬいぐるみとキャラクター人形が置かれている園で、「なぜこの人形を選びましたか」と聞くと、たいてい「寄付です」と言われました。う~ん残念!
本をまんなかに保育を語り合う ― 2025/04/27
改訂版「保育者の関わりの理論と実践」を使って園内研修を継続的に行った園へ伺ってきました。
驚いたのは、先生方の本にたくさんのポストイットがついていたり、線が引かれていたりしたことです。
私が「あれは、何ページだったかな・・・」と探していると、先生方が先に「〇ページです」と回答。
こんなに読み込んでいただいているなんて、読み合わせ用に改訂して本当に良かったと思いました。

その園では、関わりの演習が終わったとのことですので、
次は物的環境についての読み合わせをしてみませんか?とお薦めをしてきました。
保育室や園庭の環境をつくる際にも、理論が真ん中にあると、膨大な玩具の中から玩具を選べるようになります。
手作りの玩具をつくる際にも、子どもがよく遊び込む玩具を作れます。
保育はチームで行いますので、一人だけ知識があるとちょっとつらい。
本を読み合い、本を真ん中にして保育を語り合うことで、よりよい方向が見つけやすくなります。
本が真ん中にあることで、それぞれの「人」に対する意見から、「本の内容」に対する意見となり、感情的な対立が起こりにくくなります。

学びのある話し合いは上の図の左側。経験が専門性へとつながります。
話し合いだけを重ねても、専門性の向上にはつながりません。
園内研修では、一つのテーマは1~2年程度としてテーマを変えましょう。
物的環境が6割か7割できたら、次は人的環境の向上へ。
人的環境が7割できたら、次は保育内容の展開(保育者が提供する文化・活動)の向上へ。
文化の提供もある程度よくなったら、子どもの把握と理解へ。
環境構成を5年も10年も探求するのでは研修時間がもったいないです。
また一人の保育者が環境構成も関わりも内容の展開も子どもの把握も完璧というのは非現実的です。
お医者さんも美容師さんも学校の先生も、技術は人によって違いがあります。
保育でも、(私は子どもをひっぱって集団ゲームをするのが好きだ)とか(私は環境をつくるのが得意)、(自分は絵本が大好き)とかそれぞれに自分の強みがあることでしょう。
自分が得意なことを伸ばして、補い合って助け合って保育ができるといいですね。
読み合わせをしてくださっている皆さん、いつもありがとうございます。
積み木と一緒に揃えるもの ― 2025/04/20
環境の充実と共に、積み木を保育に取り入れる園が増えてきているように思います。
初めて積み木を取り入れた園では、どうやって遊びを援助すればよいのか、迷うこともあるようです。
たとえば持ち手のついた「はめ込み型パズル」は、子どもに遊び方を示してくれています。
しかし、白木の積み木は子どもが想像することで遊びが広がる素材です。
そのため最初の内は保育者が一緒に遊んだり、ときには本格的に何かを作ることで遊びが広がっていきます。
また年少のクラスでは、動物や魚、人間の人形などを置くことで、想像のきっかけになります。
近くに動物園がある園では動物人形、水族館がある園では魚など、子どもたちの体験に合わせて揃えると良いでしょう。年長クラスになると、紙や紙粘土等を使って必要なものは作ることが増えていくようです。

表情が無表情なのもよい。立てたり座ったり斜めになったり姿勢も表情豊かな人形。

人形や木を使って建物を表現。

動物人形を使って動物園を表現。小物は大きさがあり安定性が高いと遊びが広がりやすい。
感覚統合理論による大型遊具 ― 2025/04/13
見学に伺った園の保護者よりお手紙をいただき、ある公園を教えていただきました。
高崎市観音山公園にある「ケルナー広場」。
ドイツのアトリエ・ケルナー社が提供する大型遊具が設置されています。
こちらがつくられた経緯や活動の内容はNPO法人「時をつむぐ会」のページをご覧いただきたいと思います。
ケルナー遊具は、エアーズの感覚統合理論を、遊具の設計に活用しています。
また形状の特徴は、自然の樹木や地形など自然の形に近いことです。
木村歩美先生がつくる大型遊具とも考え方が共通しています。
多くの園庭にある大型遊具は遊具の”引付け力”が強すぎて、子どもが遊具に遊んでもらう状態になりやすいものです。ケルナー遊具は自然物と関わるときと同様の動きを引きだす形状をもちながらも、人工素材を用いているため耐久性が高いのはうれしい点です。隣の遊園地の跡地には子どもを遊んでくれる遊具があり、様々な大型遊具と子どもの姿を見て、遊具のあり方を考えることができました。

足元は小さな砂利で風の強い高崎でも砂が舞いにくくなっています。
とても勉強になりました。
教えていただきありがとうございました。
物語絵本・科学絵本から広がる遊びの世界 ― 2025/03/21
退職にあたり、ほとんどの本をスキャンしてパソコンへ入れましたが、研修で紹介するために数冊だけ手元に残しました。そのなかの2冊がこの本です。
物語絵本を使ったプロジェクト保育、テーマ保育の実践紹介集です。
絵本のカリキュラムが掲載されているのも押しの理由です。
つづけて2024年に続編として科学絵本、図鑑を使った保育実践が紹介された本が出ました。
4つの園の保育実践をじっくり読めます。
物的環境と人的環境にプラスして、保育者が提供する文化や体験によって
子どもたちの豊かな遊びのイメージが広がります。
環境は構成してみたけれど、玩具に遊んでもらっているばかりで
遊びが広がらないという場合には、絵本を見直してみるとよいかもしれません。
学生さんたちにもぜひ読んでほしいと、学習室用にも3冊購入しました。
保育ってなんてクリエイティブで面白い仕事なんだろうと、ワクワクが止まらない本です。
領域「環境」の視点から園に準備したい科学絵本・図鑑・写真集は、
拙書「保育内容5領域の展開」郁洋舎のp119~121の絵本リストをご活用下さい。
2025年3月末で大学を退職します ― 2025/03/10
公募情報などでお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、
定年よりも2年早く、大学を退職することにいたしました。
退職しても保育の専門性の探求を続け、10年以内には5冊目をまとめたいと思います。
日々現場で頑張っていらっしゃる皆さんと一緒に自分にできることを続けていく所存です。
研究室の整理を続けて最後まで残ったのがこれまでいただいた色紙や手紙の数々でした。

在職中にお世話になった皆さま、ありがとうございました。
そして、これからもよろしくお願いします。
このブログを読んでいるまだお会いしていない皆様、お会いした時には声をかけてくださいね。
講演や園内研修は、地域のこどものとも社さんか郁洋舎さんにご相談下さい。
環境を構成している園ほど偏差値が高くなる!? ― 2024/12/18
教育経済学者の中室牧子先生の12月11日発売の著書
「科学的根拠(デビデンス)で子育て 教育経済学の最前線」
ここに全国の園長先生方が大喜びしそうな研究が紹介されていて慌ててブログを書いています。
きっと来年、中室先生は全国の園長研修に引っ張りだこになることでしょう。
本には、「質の高い保育所や幼稚園に通うと、小学校入学後の学力が高くなる」という研究結果が紹介されています。この研究では質の高さを測るものとして「保育環境評価スケール」が用いられています。
日本の園を対象とした中室先生らの研究によると、「保育環境評価スケール」の評点が1点高くなると、小2時の算数の学力テストの偏差値が5.2高くなり、国語でも5.5高くなる(p221)というのです。
さらに園長先生の信念と、「保育環境評価スケール」で測った幼児教育の質の関係として
園長の「基礎学力重視」の信念が強いと幼児教育の質が低く、
園長の「関心・経験重視」の信念が強いと幼児教育の質が高いということもわかったそうです。
(ここまで読んでAmazonへ行ってしまう方も多いと思います)。
保育者たちが、保育の質を高めようとすると、保護者からの抵抗があります。
先の研究は改善の根拠を明快に示すものであり、保護者への説明がしやすくなるでしょう。
また、「親は、質の高い保育所や幼稚園を見抜くことができない」(p227)という内容もあり、
保育を変えることをためらう保育者の背中を押してくれそうです。
この本を追い風に、日本の保育園・こども園・幼稚園の保育環境の改善が一気に進みそうだと希望を抱きました。
「第9章 日本の教育政策は間違っているのか?」からぜひお読みください。