クラスに置く絵本選び ― 2015/04/14
4月の大変な時期に保育者を助けてくれるものは、砂場と、動物たちと、絵本と玩具。
この中で、どの園にも必ずあるのが絵本です。
初めて出会う子どもの興味や関心も、さまざまな絵本を置くことで把握しやすくなりますね。
幼児教育の機能を果たしている保育園や幼稚園には、必ず、数百冊の絵本が常設されていると思います。
保育者は、そこから自分のクラスにどの絵本を置くか、教材選択をしなくてはなりません。学校では、絵本選びの基準を学んでいても、数百冊ある絵本のなかから自分のクラスの本を選ぶのはなかなか大変。どうしても自分の好みに偏りがちです。そこでお薦めしているのが、こどものとも社の絵本カタログを活用することです。この時期、各社の営業マンがやってきて新しいカタログと古いカタログを交換しますが、園長先生に言って古いカタログをもらってしまいましょう。
2011年の「こどものとも社総合カタログ」
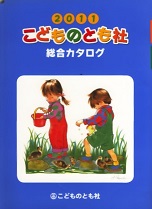
私はゼミ生用に、とも社に電話をして、回収した古いカタログを分けていただいています。
トップページに0歳から年齢ごとにお薦めの絵本があります。新人の頃はこれを目安に。

母の日、運動会など行事ごとに絵本が並べられたページも活用しやすいでしょう。

あやとりなどのあそびの本もクラスには置いておきたいですね。

保育者が、その季節に合った絵本を選びやすいように、月間ものがたり絵本や科学絵本を4月から月別に並べている園もあります。(川和保育園さんで教えていただきました)
また、絵本をあいうえお順に置くよりも、012歳児向けは別に分け、3歳以上児向けの絵本もからだに関する本、色・数・形に関する本、詩・となえ・言葉の本、シリーズ本と分けて置く方が、先生方が絵本を活用しやすくなるかもしれません。(誰か、絵本棚を卒論で研究しないかな?)
各クラスに置かれた絵本には、保育の専門性が現れます。
最近は、大人感覚の絵本も増えましたが、絵本は子どもの心の奥深くに残る物語。
子どもの文化として、絵本を選んでいきたいですね。
