がんばれ日本の保育予算 ― 2015/04/01
最近、「保育」という用語が「託児」のように用いられることが増えているため、(本来、児童福祉法の用語を改訂すべきだと思いますが)、ホームページのタイトルを変えてみました。
認定こども園は、学校教育と児童福祉の機能を併せ持つことが求められます。そこで働く保育教諭は、名前は教諭であっても、福祉専門職としての知識・技術・態度が不可欠です。
日本では貧困率が高いことや、ひとり親家庭の貧困率が著しく高いこと、先進国で税金を再配分した後に貧国率が上がるのは日本だけということはよく目にしますが、貧困問題に加えて、保育・教育予算の問題、保育の質の問題に焦点をあててわかりやすくまとめている本を教えていただきました。
山野良一「子どもに貧困を押しつける国・日本」光文社新書、2014.10
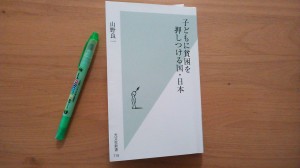
第二章 「最低の保育・教育予算、最高の学費」では、
・国際比較では、子ども一人あたりの広さの最低基準は、日本が最低レベルにあること
・国際比較では、日本は3歳以上児のスタッフ一人あたりの子ども数が多いこと
・国際比較では、日本は小学校教諭と比較して、幼稚園教諭・保育士の待遇が低いこと
・経済的に厳しい世帯の子どもであればあるほど、保育の質による発達の差が大きくなること
・人的資本投資に対する収益効果は、就学前が最も高いこと
・国際比較では、日本は3歳以上児のスタッフ一人あたりの子ども数が多いこと
・国際比較では、日本は小学校教諭と比較して、幼稚園教諭・保育士の待遇が低いこと
・経済的に厳しい世帯の子どもであればあるほど、保育の質による発達の差が大きくなること
・人的資本投資に対する収益効果は、就学前が最も高いこと
等、保育への投資を訴える上で、必要な情報が図表を使ってコンパクトにわかりやすくまとめられています。
この本では、貧困な状況にある子どもほど、質の高い保育の効果が高いことにもふれられています。保育園と認定こども園は、質の高い教育と福祉の提供によって不幸の連鎖を防ぐという社会的な役割があることも忘れないようにしたいものです。
*最初はタイトルを、「最低の保育・教育予算」としていましたが、ネガティブなので変えました。
保育士が働き続けられるために ― 2015/04/07
保育士不足が深刻です。その最大の原因は、職務内容に比べて待遇が低すぎることだと言われています。
命を預かる責任は重く、肉体的にも重労働でありながら記録や計画といった頭脳労働も多い。幅広い知識、教育とケアの専門性と自己研さんが求められる福祉の専門職です。毎日が総合学習であり、個々の保育士の裁量の幅が広い仕事。創造的で自律的な人が、やりがいを感じられる仕事です。
保育所の場合、福祉ニーズの高い家庭が利用するため、特別な支援を必要としている子どもと保護者もいます。保育士に求められる職務内容と専門性は高いけれども、記録と準備の時間は幼稚園のように確保されていません。夏期休暇や年度末休暇も交代制です。保育士の待遇は職務内容とは見合わず低いものです。
保育士の待遇は、今後わずかに改善される見込みがありますが、過重な仕事量は、各園で工夫して減らす必要があります。保育所は長時間保育になり、特別に支援を必要とする子どもが増え、計画や記録の量も増えています。1歳児でも20人以上などクラス規模も大きくなっています。この状況のなかで仕事を減らさなければ、保育士の負担は増える一方です。今回は、保育士が保育を続けることができ、就職希望者が増えるために、園長・主任が中心になって行っている各園の工夫を紹介してみます。
保育士の「しなくてもいい苦労」を減らす
〇保育室・園庭の保育環境を変える。物的環境は人的環境をカバーする。
〇子ども主体の保育に変える。子どもに指導をし続ける保育は、保育士の精神的・肉体的な疲労が大きい。
〇一人ひとりの差異を受け止められる流れる保育に変える。発達に合わない一斉保育は保育士の負担が大きい。
〇ゼロ12歳児の保育を、担当制にする。
〇ゼロ123歳のクラス分けを年齢別ではなく、その年度の子どもの様子に合わせて柔軟に変える。クラス集団の大きさが小さくなるようにする。
〇発達に合う行事に変える。保育士の過剰な指導が必要な行事は発達に合っていないため改善する。行事は、日常の保育を見せることを重視し、行事前に連日残業をして飾りや衣装を作ることを防止する。
〇計画と記録を省略化する。実践に使いやすい計画や記録を作る。前年までの記録や計画は閲覧可にする。
〇計画と自己研さんに必要な参考資料を貸出し、園での遊びや活動を蓄積、ファイル化する。
〇園に遅くまで残ることがいいこと、という雰囲気があれば、それをなくす。
〇作り物を減らす。壁面飾りは作らず本物の季節飾りを置く。準備が必要なお持ち帰り型の工作は減らし、準備が不要な日常的に使える造形の素材をたっぷりと準備し、日常的な造形表現を写真で残す。
〇国の最低基準以上の保育士を配置する。(そのため一人当たりの給与が低くなっている園もある)。
〇必要な計画・記録・製作時間の確保のために、パート職員を雇用する。
〇保育士の業務内容を減らす。製作や掃除等委託できる作業はボランティア希望者や無資格者の雇用で補う。
〇洗濯乾燥室など、保育士の労働が軽減できる機械を整備する。
〇職員会議で「残業を減らすには」、「就職希望者が増えるには」と、ブレーンストーミングで意見を出し合う。
保育士の過剰なストレスを減らす
〇職員が辞める原因となる職員の行動がある場合は、園長と主任、園長と理事長など複数で対処し放置しない。
〇保護者の相談は、主任や園長が中心に受ける。
〇保護者には、入園時に国の保育士の配置基準を説明し、理解を得ておく。
〇お迎えの時間には、園長か主任が園内や園庭に出て保護者に声をかけていく。
〇保護者とのトラブルや事故対応は、主任や園長が責任をもって対応する。
〇人格障害に対する基本的な知識を学習し、職員集団が振り回されないようにする。
〇福祉ニーズが高い家庭の割合が高い園は、保育士の増員やソーシャルワーカーの配置を市に要求する。
〇それぞれの保育士が得意なことを発揮し、お互いに補い合い、助け合うことを推奨する。全員に一律の能力を求めない。ピアノが得意な人、手作りが得意な人、研修・研究が得意な人など強みを発揮できるようにする。
保育士がリフレッシュできる仕組みをつくる
〇まとめて休みがとれるようにする。4月~6月の間に一週間続けて休みを取る仕組みを作っている。
〇仮眠、休憩、保育中にお茶を飲むなど、保育士がリフレッシュすることは良いことだという文化をつくる。
〇保育士が、子どもと離れてゆっくり休憩ができる場所を複数作っている。
〇保育士の休憩室には、仮眠ができる機械が置かれている。(休憩室にマッサージ機があれば、肩こりによる頭痛がどれだけ減るだろう)
〇園長が落ち込んでいる職員に、ボケたりつっこんだりする。(状況と相手によっては逆効果の場合も?)
〇園の慰労会では、園長先生のポケットマネーでビンゴ大会を行っている。
保育士が、自分で自分の仕事をコントロールしている感覚をもてるようにする
〇保育士たちが最も保育に合った週日案、記録を考え、書式を柔軟に変更する。図を使う。マインドマップをそのまま計画にしている。文章に書き替えない。
〇保育環境は、知識を持った上で保育士たちが話し合って決め、変えることを推奨する。
〇絵本、遊びの素材等は保育士が購入できるようにする。カタログ等は保育士が閲覧する場に置く。
〇当番研究やテーマが固定された研究には希望者が参加し、自分たちが必要な園内研究をする。
自己肯定感や、やりがいを感じられるようにする
〇できるだけ多くの保育士が、質の高い研修に出られるように工夫する。
〇質の高い保育を行っている園を、保育士が見学する研修を組む。
〇外来者(研究者や小学校教員等)、保護者の前で、その保育士の良い面を話す。
〇手柄は、保育士のものにする。
〇職員の名前を書いた手帳に気づきを書き込み、いいところリストをつくっている。
〇子どもが日々幸せにすごせる保育への改善を推進する。
〇保育士が誇りをもてる質の高い保育への改善を推進する。
これまでの園訪問で、園長先生方や主任の先生方から教えていただいたことをまとめてみました。
いきいきと保育者が働いている園は、意外に園長先生が保育経験がない場合がありました。自分が経験がないために、本気で(大変だよね、頑張っているよね)と感じている、そして(どうすればもっと保育者が楽しく仕事ができるだろう)と試行錯誤されている園長先生方と出会い、経験がないことがプラスに働く部分もあると気づきました。
子どもの保育も、保護者の支援も、保育士の労働のマネジメントも、当事者の力量で考えることが基本です。現実の今の保育者集団の力量を捉えて、どこをどう変えればよいかを考えていく、また保育士が頭を突き合わせて考えていけば、その園にちょうどいいやり方が見つかるかもしれません。

クラスに置く絵本選び ― 2015/04/14
4月の大変な時期に保育者を助けてくれるものは、砂場と、動物たちと、絵本と玩具。
この中で、どの園にも必ずあるのが絵本です。
初めて出会う子どもの興味や関心も、さまざまな絵本を置くことで把握しやすくなりますね。
幼児教育の機能を果たしている保育園や幼稚園には、必ず、数百冊の絵本が常設されていると思います。
保育者は、そこから自分のクラスにどの絵本を置くか、教材選択をしなくてはなりません。学校では、絵本選びの基準を学んでいても、数百冊ある絵本のなかから自分のクラスの本を選ぶのはなかなか大変。どうしても自分の好みに偏りがちです。そこでお薦めしているのが、こどものとも社の絵本カタログを活用することです。この時期、各社の営業マンがやってきて新しいカタログと古いカタログを交換しますが、園長先生に言って古いカタログをもらってしまいましょう。
2011年の「こどものとも社総合カタログ」
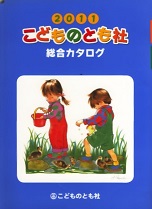
私はゼミ生用に、とも社に電話をして、回収した古いカタログを分けていただいています。
トップページに0歳から年齢ごとにお薦めの絵本があります。新人の頃はこれを目安に。

母の日、運動会など行事ごとに絵本が並べられたページも活用しやすいでしょう。

あやとりなどのあそびの本もクラスには置いておきたいですね。

保育者が、その季節に合った絵本を選びやすいように、月間ものがたり絵本や科学絵本を4月から月別に並べている園もあります。(川和保育園さんで教えていただきました)
また、絵本をあいうえお順に置くよりも、012歳児向けは別に分け、3歳以上児向けの絵本もからだに関する本、色・数・形に関する本、詩・となえ・言葉の本、シリーズ本と分けて置く方が、先生方が絵本を活用しやすくなるかもしれません。(誰か、絵本棚を卒論で研究しないかな?)
各クラスに置かれた絵本には、保育の専門性が現れます。
最近は、大人感覚の絵本も増えましたが、絵本は子どもの心の奥深くに残る物語。
子どもの文化として、絵本を選んでいきたいですね。
ロッカーの配置と保育内容 ― 2015/04/23
最近、保育園の新設が盛んですが、改築した園舎を見せていただくことも増えました。
これまで見せていただいた新しい園舎は、大きく二つに分かれました。
一つは、これまでとは違う新しい設計の園舎です。もう一つは、建物は確かに新しいけれども、古い園舎とほぼ同じ設計です。最も違いがあるのが、子どものロッカーの場所なんです。
古い保育室は、どこも保育室の壁にロッカーがありました。ミニ小学校仕様です。先生が今日は何をするか指示をし、子どもは小学校と同様に先生の指示に従って課業をします。そのため室内の環境は、それほど重要ではありませんでした。子どもが先生の指示に従って動くためには、ロッカーが壁にある方が、むしろ効率的だったのかもしれません。
新しい設計では、「前室」と言われる空間があったり、ロッカーを遊びの空間とはゆるやかに分けて配置していたり、移動式のロッカーを使用していたりします。子どもが発想をひろげ豊かで継続的な遊びを展開できるように保育室の壁にはロッカーがありません。壁にロッカーがないことで保育者は環境構成を行いやすくなり、子どもの主体的で個別的あるいは協同的な活動や、遊びを通した学びを援助しやすくなります。

生活の空間と遊びの空間がゆるやかに分けられている保育室の例(青葉保育園、1歳児クラス)
ロッカーが壁にないだけで、保育室内のゴチャゴチャ感が半減し、視覚の刺激に弱い子どもが活動に集中しやすくなる利点もあります。また室内の動線が変わると、保育はとても楽になります。空間がわかりやすいと、子どもは自分で判断し行動するため、大人の指示が減ります。
新築ができないからと、壁からロッカーをはがして移動してしまった園も複数拝見しました。先生方の熱意には頭が下がります。
学びの土台となる「自律」 ― 2015/04/30
小学館「新幼児と保育」6・7月号(5月2日発売予定)の「学びの土台となる保育環境」のテーマは、「自律」です。
取材のために伺った園は、千葉県富津市にある「和光保育園」。二度目の訪問です。
取材記事では幼児の生活が詳細に写真で紹介されます。入りきれない内容と補足説明を、ここに書きますね。

取材した日は3月半ば。引っ越しの会が終わり、新しい部屋へ子どもたちが移動して3日目でした。新入園児が入ってくる前に、一足早く進級する部屋に引っ越しをして、生活になじんでから新しい園児を待つことにしていらっしゃるそうです。「まだ落ち着かない状況ですが」と言われましたが、なんのなんの。生活場面の落ち着きには驚きました。

1歳児クラスに移動したばかりの子どもたち。先生のお手伝いをしたくてたまりません。
1歳(正確には0歳児の3月)のクラスでも、子どもたちが食事の時間だとわかると、自分で椅子を運んで来たり、保育者の手伝いをしようと、それぞれの子どもが、自分なりに考えて食事をしようと準備をしていました。どの子どもも自分で椅子に座ります。何と誇り高いこの姿。この子どもたちは小学校でもレストランでも、まわりの状況を自分で判断して行動することができるだろうと、うれしくなりました。

0歳のクラスから1歳の部屋へ移って3日目の食事の様子。普通の1歳児クラスの食事場面とどこが違うでしょうか?
先生や大人に、指示をされて生活する習慣をつけている子どもは、こうはいきません。指示されるから、怒られるから行動するという心の癖がついている場合には、新しいクラスになるとひっちゃかめっちゃか、怒られない場所だと大騒ぎ、小学校へ行ったとたんに先生の話を聞かなくなります。
先生方は大きな声で指示を出しません。子どもたちが生活の主人公になるように、環境をつくり必要な援助をされていました。これは、自由放任や放縦とは違います。子どもたちの様子を大らかに見守りながら、余裕をもって保育をされる姿が素敵です。また先生方は、子どもたちの育ちに合わせて、食事の準備の方法や、集団で食べるタイミングを変えていらっしゃいました。

3歳児クラスに移動したばかりの2歳児の子どもたち。幼児クラスの詳しい生活の流れは「新幼児と保育」の記事で。
日本の学力観は、知識・技能を習得することから、知識・技能を使った「思考力・判断力・表現力」へと、変化しています。学習指導要領でも、基礎・基本を使って、「自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力」が重視されています。このような学力の土台をつくる幼児教育では、子ども自身が自律的に行動する生活と、子どもが工夫し創造できる教材や活動が大切になります。
昭和の高度成長期時代に求められた能力と、国際化し変化が激しい時代に持続可能な福祉社会をつくる能力は異なります。先生から言われるまでじっと待っている、先生から言われたことしかしない心の習慣をつけてしまうと、学童期以降は大変です。また、幼児期に、遅い子どもは悪い子(先生に叱られる子)、みんなと違うことは悪いことという価値観を獲得させることは、いじめの種を蒔くことにもなるかもしれません。
以前授業で、動画サイトにアップされた様々な保育を見て、「その保育を受けた子どもはどのような価値観を持つようになるか」、「その子どもたちに向く職業はどんなものか」を考えたことがあります。0歳からの一斉活動に一斉排せつ、自分で考え工夫すると叱られる保育内容の場合、「先生の言うとおりにしなくてはいけない」、「みんなが同じで一緒であることがいいこと」という価値観をもち、向く職業には、「ブラック企業」という声が上がりました・・・。
深い理念と経験をもつ世代と、若く心優しい世代が一緒になって、競争のパラダイムから共創のパラダイムへと保育を変えていきたいものです。
